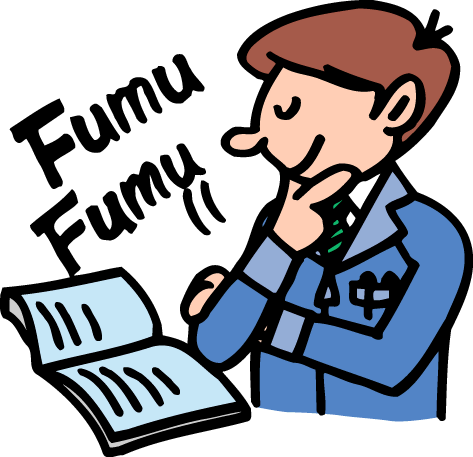
| セミナー・記事 |
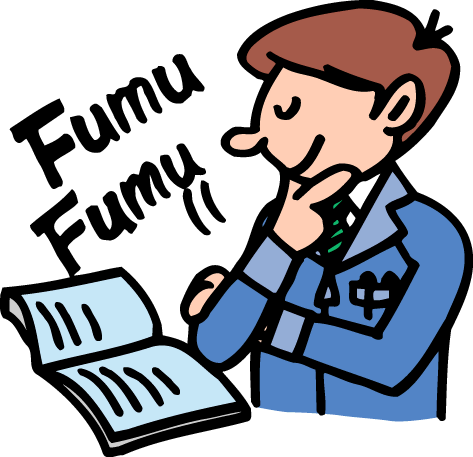 |
セミナー・講演会
| 生産性20%向上、不良1/5を実現する SMT(表面実装)ラインのムダとり |
1999.11.5 | 東京機械新興会館 主催 ㈱新技術開発センター |
| SMTラインの無駄とり手法 | 2000.1.20 | 東京ビックサイト 主催 ㈱工業調査会 |
| Just-in-Timeに向かっての 在庫のあるべき姿 |
2001.11.8 | JA長野県農協ビル 主催 富士通ファミリー会 |
| 誰でもできる製造リードタイム半減術 | 2002.8.28 | 東京・ホテルB&G 主催 ㈱新技術開発センター |
| 今体質を変えないと企業は生き残れない | 2002.12.7 | 松本・ ピレネ 中信トラック協会研修会 |
|
企業の中における管理者の スタンスと行動はどうあるべきか |
2003.2.24 | メルパルク長野 (株)丸正新春幹部会議 |
|
日本のモノづくりはこれでしか生き残れない なぜ リードタイムの短縮が必要なのか |
2003.4.24 | 日置電機株式会社 7階 研修室 Hips 特別企画 お取り引き様向けセミナー |
| ISOで業務改善を実現する手法とノウハウ | 2007.3.30 | 日本テクノセンター 研修室 主催 日本テクノセンター |
| 経営・業務改善に役立つISO9001徹底活用術 | 2007.6.15 | 大阪府商工会館 主催 (社)大阪府工業協会 |
| ISOを使いたおす! ISO9000規格を積極的活用するための講演会 |
2007.7.13 | 長野県工業技術総合センター 主催 (社)中部電子工業技術センター |
| 「取得から実践へ、 ISOをこうやって使いこなそう!」 |
2007.8.8 | 兵庫県姫路市 高菱エンジニアリング株式会社様セミナー |
| ISOは日常業務に役立ち、 企業に利益をもたらす |
2007.11.5 | さいたま市 新都心ビジネス交流プラザ 彩の国ISO研究推進協議会 |
| ISOを経営改善のために活用しよう! | 2008.11.25 | 株式会社 日本触媒 姫路製造所様向けセミナー |
| 会社の運営に行き詰まる前に読む本 から | 2013.11.15 | 日本鍛圧機械工業会 中小企業青年委員会 |
| 内部監査員に求められるのは、 問題発見能力と、 それを改善していく展開力だ! |
2014.7.11 | 日本規格協会 文京シビックセンター 小ホール |
| 2014.9.3 | 日本規格協会 品川 きゅりあん |
|
| 2014.9.10 | 日本規格協会 大阪市中央公会堂 |
|
| 改善活動を推進するために必要なこと | 2019.11.11 | 長野県茅野市 三社電機イースタン樣 講演会 |
| 記 事 |  |
| SMTのUライン | 1998.10月号~1999.2月号
4回連載 |
【エレクトロニクス実装技術】 ㈱技術調査会 |
| 生産性が4倍になった 組み立てライン |
2000.11月号 | 【工場管理】 ㈱日刊工業新聞社 |
| 受注の変動に対し、 いかにして効率よく 材料を供給するか 18回連載 |
【工場管理 】 連載 ㈱日刊工業新聞社 | |||
| その1 | 発注残に注目する | 2001年 | 2月号 | |
| その2 | 簡単な仕組みを作ってみる | 2001年 | 3月号 | |
| その3 | 納期確認ラインを作るPart1 | 2001年 | 4月号 | |
| その4 | 納期確認ラインを作るPart2 | 2001年 | 5月号 | |
| その5 | 納入リードタイムを解明する | 2001年 | 6月号 | |
| その6 | 材料調達の方法を考える | 2001年 | 7月号 | |
| その7 | 私のプレゼンテーション | 2001年 | 8月号 | |
| その8 | 実需材料調達の実践 Part 1 | 2001年 | 9月号 | |
| その9 | 実需材料調達の実践 Part 2 | 2001年 | 10月号 | |
| その10 | 売れ方に合ったモノ作り | 2001年 | 11月号 | |
| その11 | 受注の変動に対応する | 2001年 | 12月号 | |
| その12 | 在庫を削減させる | 2002年 | 1月号 | |
| その13 | 工程の改善が重要 | 2002年 | 2月号 | |
| その14 | 売れ残り在庫をゼロにする | 2002年 | 3月号 | |
| その15 | 生産リードタイムを短縮する | 2002年 | 4月号 | |
| その16 | 材料を供給する側のスタンス | 2002年 | 5月号 | |
| その17 | 緊急発注が発生する | 2002年 | 6月号 | |
| その18 | 部品を標準化する | 2002年 | 7月号 | |
| 現場が求める検査機の役割と機能 | 2002.9月号 | 【エレクトロニクス実装技術】 (株)技術調査会 |
| 活躍する修了生 男の舞いを舞ってみよ! |
2002.10月号 | 【社員教育】 社員教育研究所 |
|
インサートマシンの能力を100%引き 出した コーセルの設備保全活動 ~古い設備が新しい生産体制の機軸になる |
2003.1月号 | 【工場管理】 (株)日刊工業新聞社 |
| 日本で生き残るための生産革新 現場からスタートさせた 日置電機のHiPS活動 |
2003.10月号 【記事の詳細】 |
【工場管理】 (株)日刊工業新聞社 |
| 日本で生き残るための生産革新 限りなくサービス業に近いモノづくり 日置電機のHiPS活動 |
2005.10月号 【記事の詳細】 |
【工場管理】 (株)日刊工業新聞社 |
| ~地域に根ざしたモノづくり~ 中小企業のパワーの源泉は 技術力と改善力とチャレンジ精神だ (株)アルゴル |
2006.5月号 【記事の詳細】 |
【工場管理】 (株)日刊工業新聞社 |
| このままでいいのか? 中小企業のISO活動 |
2007.11月号 【記事の詳細】 |
【プレス技術】 (株)日刊工業新聞社 |
| 変えようと思っても変われない会社 生産革新に弾みがつかないホントの理由とは? |
2008.2月号 【記事の詳細】 |
【プレス技術】 (株)日刊工業新聞社 |
| 顧客から、社会から 信用されるメーカーになるということ (上・下) |
2008.
4月号 2008. 6月号 【記事の詳細】 |
【プレス技術】 (株)日刊工業新聞社 |
| どうしたら「会社の一体感」は生まれるか? ~意識をひとつにするための秘訣~ |
2008.10月号 【記事の詳細】 |
【プレス技術】 (株)日刊工業新聞社 |
| 続・くたばれ!ISO。 | 2009. 4月号 | 【ISOマネジメント】 (株)日刊工業新聞社 |
| 生産技術者が取り組むべき改善活動 第1回 カイゼンに臨む生産技術者の心得 第2回 カイゼンの前提条件を理解しよう 第3回 段取り替え作業の真髄を見極めよう 第4回 個別最適ではない段取り改善の勧め 第5回 垂直立ち上げを実現するノウハウを 体得しよう |
2010.
5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 |
【プレス技術】 (株)日刊工業新聞社 |
| 考察 新たな一歩を踏み出す方向 ありたい工場環境の絵を描くために |
2011. 6月号 | 【プレス技術】 (株)日刊工業新聞社 |
| 新要員立上げ記念講演会 概要 | 2014年 11月 【記事の詳細】 |
【JRCA NEWS Vol14】 (財)日本規格協会 |
工場運営の光と影 【工場管理】 連載 (株)日刊工業新聞社
| 第1話 | 欲しいモノを、欲しいときに、欲しい数だけ購入したいのです! | 2006年 | 8月号 | ||
| 第2話 | 間接部門の個人机は撤廃してしまわないと問題が見えてこない。 | 2006年 | 9月号 | ||
| 第3話 | 設計変更は管理するな。部品の在庫から実施する時期の信号を発信せよ。 | 2006年 | 10月号 | ||
| 第4話 | 中小企業では、かんばんによる部品調達が機能しないから困ってしまう。 | 2006年 | 11月号 | ||
| 第5話 | 「納期を守るためには何をすればよいか」を常に考えることが大事。 | 2006年 | 12月号 | ||
| 第6話 | 在庫を持つことがムダを見えなくし、 リードタイムが長いことが原価を押し上げる。 |
2007年 | 1月号 | ||
| 第7話 | コンピュータのシステムは工場の問題を解決してくれるのか? | 2007年 | 2月号 | ||
| 第8話 | まずは発生している問題を解決しないと改善は現場に定着しない。 | 2007年 | 3月号 | ||
| 第9話 | 品質保証部は、何によって製品の品質を保証していくのか? | 2007年 | 4月号 | ||
| 第10話 | ISO9001を取得している工場で、なぜ品質問題が発生してしまうのか? | 2007年 | 5月号 | ||
| 第11話 | 5Sが定着している現場では、本当に問題の発生が減少しているか? | 2007年 | 6月号 | ||
| 第12話 | 流すことでムダが見えるようになり、停滞がなくなることでコストが下がる。 | 2007年 | 7月号 | ||
| 第13話 | 在庫を減らすためにはプロセスの改善が必要になってくる。 | 2007年 | 8月号 | ||
| 第14話 | 品質は痛みを伴わないとなかなか向上していかない。 | 2007年 | 9月号 | ||
| 第15話 | セル生産を何のために導入するのかはっきりさせよう。 | 2007年 | 10月号 | ||
| 第16話 | 棚卸しは仕事の進め方の問題を発見するために行うのだ。 | 2007年 | 11月号 | ||
| 第17話 | 多品種少量生産の実現は段取り替えの改善が条件になる。 | 2007年 | 12月号 | ||
| 第18話 | 企業が人を育てるのに難しい時代背景だから より明確なプランが必要になる。 |
2008年 | 1月号 | ||
| 第19話 | 「見える化」は、誰に何が見えるようにすればいいのか。 | 2008年 | 2月号 | ||
| 第20話 | 多能工の育成は高望みをせずに現実に合わせた方法で進めよう。 | 2008年 | 3月号 | ||
| 第21話 | 財務会計を、問題を発見するための管理会計に移行させよう。 | 2008年 | 4月号 | ||
| 第22話 | 会議は何を目的として実施され、本当に有効に機能しているのだろうか。 | 2008年 | 5月号 | ||
| 第23話 | 性悪説がベースになっているうちは 社員の能力を引き出すことはできない。 |
2008年 | 6月号 | ||
| 第24話 | 品質の悪さ加減を工場の壁に貼り出すことができるか。 | 2008年 | 7月号 | ||
| 第25話 | 営業活動に必要なのは、戦略を組み立てるための明確な方向性だ。 | 2008年 | 8月号 | ||
| 第26話 | 普段あたりまえに思っていることも、 ちょっと切り口を変えて見ると不思議な現象なのだ。 |
2008年 | 9月号 | ||
| 第27話 | 部品の標準化は購買部が推進するのがいちばん適している。 | 2008年 | 10月号 | ||
| 第28話 | マニュアルが整ってさえいれば仕事がうまくいくというのは 幻想にすぎない。 |
2008年 | 11月号 | ||
| 第29話 | 経費を削減することが経営者の仕事ではない。 | 2008年 | 12月号 | ||
| 第30話 | 誰かが体を張らないと品質はなかなか向上していかない。 | 2009年 | 1月号 | ||
| 第31話 | 部門別採算性の行き過ぎた追求は新たな歪みを発生させる。 | 2009年 | 2月号 | ||
| 第32話 | 何をやるかでなく何をやってきたかが問われる時代だ | 2009年 | 3月号 | ||
| 第33話 | 減量経営を実行するときには従業員のモチベーションの維持を図ること | 2009年 | 4月号 | ||
| 第34話 | 面倒くさいことをわざわざ行うことによりムダを顕在化させるのだ | 2009年 | 5月号 | ||
| 第35話 | 工程差し立て板の導入により現場に自律機能を持たせる | 2009年 | 6月号 | ||
| 第36話 | 受ける人が求めていることと合致しないと教育の本当の効果は生まれない | 2009年 | 7月号 | ||
| 第37話 | 経営改善の三本柱がかみ合えば企業の体質を変えることができる | 2009年 | 8月号 | ||
| 第38話 | 「QC工程表」は工程の能力を高める働きをしているのだろうか | 2009年 | 9月号 | ||
| 第39話 | QCサークルはなぜ盛り上がりに欠いたのか | 2009年 | 10月号 | ||
| 第40話 | 制約条件を与えていかないと仕事のレベルは向上していかない | 2009年 | 11月号 | ||
| 第41話 | 究極のモノ作りを追求している食品工場 (上) | 2009年 | 12月号 | ||
| 第42話 | 究極のモノ作りを追求している食品工場 (中) | 2010年 | 1月号 | ||
| 第43話 | 究極のモノ作りを追求している食品工場 (下) | 2010年 | 2月号 | ||
| 第44話 | 見せかけの原価ではなく本当の原価を追求していこう | 2010年 | 3月号 | ||
| 第45話 | 営業の秘訣はお客様に迷惑をかけることである | 2010年 | 4月号 | ||
| 第46話 | 設計の工程にキャパがあるなどと考えていると、 日程の遅れを挽回することはできない |
2010年 | 5月号 | ||
| 第47話 | 生産試作とフィールドテストを実施して不良の市場への流出を防止する | 2010年 | 6月号 | ||
| 第48話 | 数値を眺めていただけでは本当のムダを発見することはできない | 2010年 | 7月号 | ||
| 第49話 | 「見える化」で現場のムダが明らかになっているのだろうか | 2010年 | 8月号 | ||
| 第50話 | 材料の調達方法を棚卸ししてみる | 2010年 | 9月号 | ||
| 第51話 | 生産管理部門の仕事は日程をコントロールすることだけではない | 2010年 | 10月号 | ||
| 第52話 | 立ち上げがうまくいくかいかないかは事前の準備の質で決まってくる | 2010年 | 11月号 | ||
| 第53話 | サプライチェーンマネジメントは相手の条件も整えるべきである | 2010年 | 12月号 | ||
| 第54話 | 生産性を評価する数字は能率ではなく稼ぎ高に置きかえよう | 2011年 | 1月号 | ||
| 第55話 | 不良の解析は原因にたどり着くのをあわてるな | 2011年 | 2月号 | ||
| 第56話 | 設備の保全活動は、まずはデータを集めることからはじめる | 2011年 | 3月号 | ||
| 第57話 | 多能工化は前後の工程をまずひとつ修得することから始める | 2011年 | 4月号 | ||
| 第58話 | 事業仕分けで学んだことを企業の経営に生かすためには | 2011年 | 5月号 | ||
| 第59話 | コミュニケーションとは個性を生かすことである | 2011年 | 6月号 | ||
| 第60話 | 東日本大震災から私たちが汲み取らなければならないこと | 2011年 | 7月号 | ||
| 第61話 | 新入社員を早期に戦力化させるためにやらなければならないこと | 2011年 | 8月号 | ||
| 第62話 | 立場の違いは自分自身に与えられた試練でもあるのだ | 2011年 | 9月号 | ||
| 第63話 | 間接部門のムダは ヒトの中に仕事が埋もれてしまうこと | 2011年 | 10月号 | ||
| 第64話 | 「権利」は、みんなが支え合うことによって生み出されるもの | 2011年 | 11月号 | ||
| 第65話 | 「作業」を「仕事」へと転換させるためにやらなければならないこと | 2011年 | 12月号 | ||
| 第66話 | 3現主義とはすべての発想を事実からスタートさせることだ | 2012年 | 1月号 | ||
| 第67話 | 「財務会計」と「戦略会計」をドッキングさせれば問題が見えてくる | 2012年 | 2月号 | ||
| 第68話 | 変動に対応するためには固定された生産現場があることが前提になる | 2012年 | 3月号 | ||
| 第69話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ① | 2012年 | 4月号 | ||
| 第70話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ② | 2012年 | 5月号 | ||
| 第71話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ③ | 2012年 | 6月号 | ||
| 第72話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ④ | 2012年 | 7月号 | ||
| 第73話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ⑤ | 2012年 | 8月号 | ||
| 第74話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ⑥ | 2012年 | 9月号 | ||
| 第75話 | コーポレートガバナンスを社員の目線で捉えてみる ⑦ | 2012年 | 10月号 | ||
| 第76話 | 他人に対する好き嫌いの感情は私生活の場にとどめておくこと | 2012年 | 11月号 | ||
| 第77話 | 「遊び」人間にならないとなかなか自分を変えることができない | 2012年 | 12月号 | ||
| 第78話 | ときには部下が上司の統率力を評価してみるのもいい | 2013年 | 1月号 | ||
| 第79話 | 叱るのは1対1で行いそのあとのフォローを忘れないこと | 2013年 | 2月号 | ||
| 最終話 | 個人面談のあと苦い思いをするようならそれは成果があったということ | 2013年 | 3月号 | ||